FIRE目標設定の要素として以下の3つの要素を上げました。
1.目標資金
2.目標期間
3.目標生活レベル
順序は逆になりますが、今回は上にあげた中の3つ目、「目標生活レベル」について考えてみたいと思います。
FIRE(経済的自立と早期リタイア)を目指す上で、意外と見落とされがちなのが「目標生活レベル」の明確化です。FIRE達成後にどんな暮らしを送りたいのかを具体的に描くことは、目標資金を正確に算出し、計画を進めるための大きなカギになります。
また自身がFIREをやり遂げるためのモチベーションも維持しやすくなります。本記事では、私が目標生活レベルを決めるために考えた内容やポイントなどをお伝えしたいと思います。あなたのFIREプランの第一歩として、ぜひ参考にしてください!
目標生活レベルとは?
目標生活レベルとは、FIRE達成後に自分が送りたい生活の具体的なイメージや水準のことです。これは、生活費や必要資金を計算する際の基準となるため、FIREプランを考える上で非常に重要です。
今回は以下の要素を考慮して考えていきたいと思います。
- 現在の家族構成と予定
- 住居の場所や規模
- 固定費
- 食費や外食頻度
- 趣味や旅行の回数
- 医療や保険の費用
- 予備費や贅沢品への支出
これらを具体的にすることで、FIRE後の生活が現実味を帯び、モチベーションの維持にもつながります。
何人家族?ご家族が増える予定は?
様々な家庭の形があると思います。1人暮らし、パートナーと2人、お子さんが1人あるいは2人、御両親と同居など。
現状の把握は簡単にできるとしても、将来の予定を考えるとなかなか難しいと思います。考えていなかったことが起こる可能性もあります。一人暮らしの方が良いご縁があって結婚をするとか、お子さんが生まれて家族が増えるとか。あまり考えたくはありませんが離婚をしてしまうことがあるかもしれません。
あまり先のことまで考えすぎても進めなくなってしまいますので、まずはごく近い将来、起こる可能性のあることに焦点を当てるようにしましょう。何か大きな変化があれば、その時に見直せばいいのですから。
私の現状は妻と子供が1人の3人暮らしです。妻はフルタイムで働いており、定年年齢は未確定ですが60歳を少し上回るようになりそうです。子供は私立に通う高校生で大学に進学予定です。本人は私立の文系に進むつもりなので、その予定にしています。
ありがたいことに大阪では私立高校の授業料が無料になり、かなり負担が減ることになっています。
私はというと、55歳時に退職し、主夫をしつつブログを書いております。
どこに住むか?どんな住居を選ぶか?持ち家?借家?
次に住居の場所や規模を考えたいと思います。
これに関しても、ご家庭によっていろいろ違ってくると思います。
戸建てをローンで返済中の方、転勤が多いため賃貸で暮らしておられる方、マンション住まい、実家で親族と住んでおられる方、などそれに伴い必要なお金も様々でしょう。
これらを明確にしておく必要があります。
今後家を買うのか、それとも賃貸で暮らすのか、ローンを組むもしくは組んでいるのなら返済はいつまでなのか?このあたりをイメージしておくことは重要です。
現在、私は関西にてマンション暮らしをしています。すでにローンの返済は終わっていますので、必要な金額は毎月の管理費や修繕積立金と保険代、固定資産税になります。
したがって今の住居に住み続けるのなら、毎月3万円ぐらいの支出が必要になります。
余談ですが、修繕積立金、高いですよね。ちょっとずつ値上がりしていきますし。インフレが進んでいくとちょっと不安です。
さて、少なくとも子供が就職するまでは今の住居で暮らすつもりですが、就職先がどこになるかでこの家をどうするかを決めることになります。通勤圏内であれば子供にそのまま住んでもらってもいいですし、引っ越しするようなら貸し出したり売ったりすることも可能です。
この辺りはそうなった時に見直す必要があります。
なんで自分でそのまま住まないのか?という疑問が出てくるとお思いでしょうが、実は妻の親が地方に使っていない家を所有しているんです。古民家などではなく、築40年程度の昭和の古家といった感じで、いろいろと手直しするところはありますが、現在でも住むことはできる状態を維持しています。
ですので、子供が大学に入って手がかからなくなったら、まずは私だけでもお試し移住をやってみようと考えています。
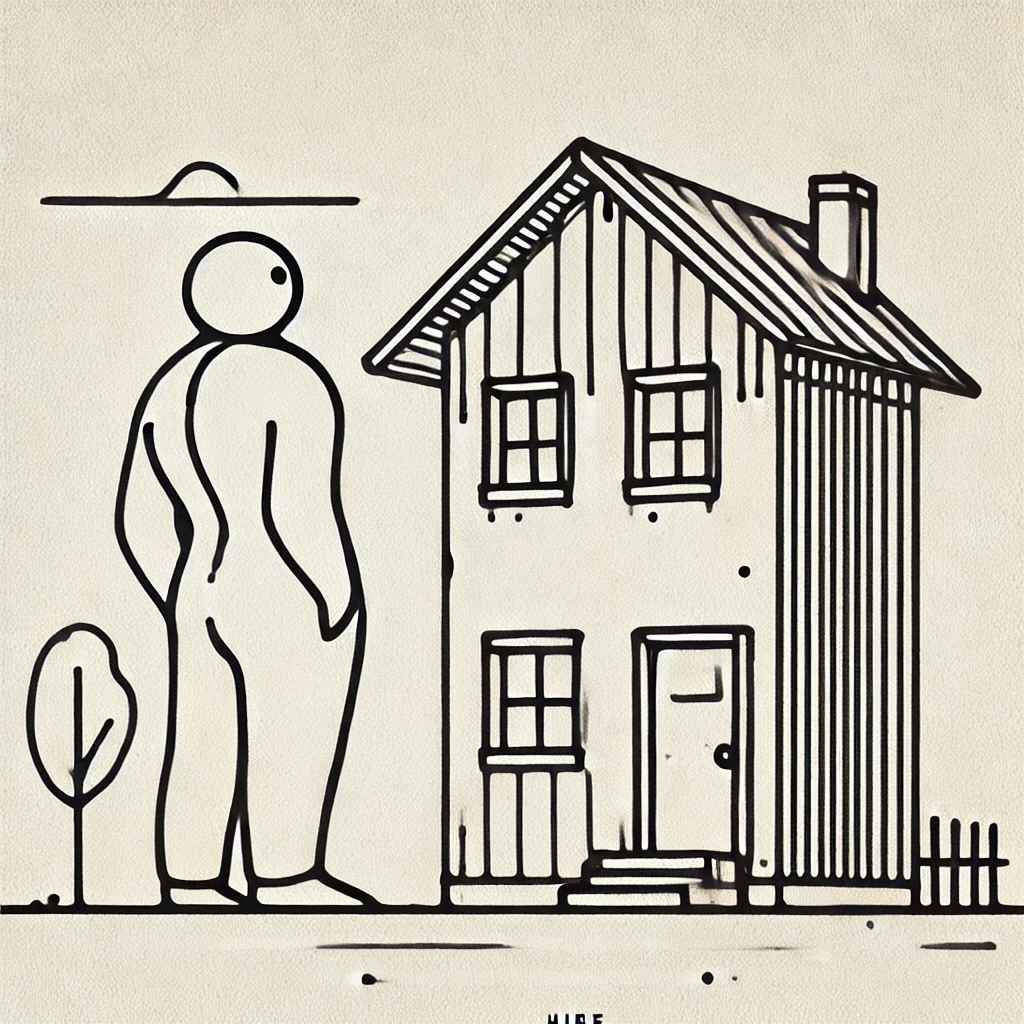
固定費はどのくらいかかっていますか?
節約を始めるときに一番最初に確認を行うポイントとしてよく話題にされます。
生命保険、新聞代、スマホなどの通信費、動画のサブスクや電気、ガス代まで様々なものがサブスクとして挙げられます。ジムに通っておられる方はそれも含まれますね。
自分では必要だと思って契約したはずだけれども、実際には全く使っていなかったとか、契約したことすら忘れてしまっていたなんてこともあるかもしれません。
実際にクレジットカードの明細を見て自分の固定費を書き出してみることをお勧めします。
私の2024年12月のクレジットカードの明細から実際に抜き出してみたものが下記のものです。
- 携帯、固定光通信費 12000円
- 公共料金(電気ガス水道) 20000円
- マイクロソフトオフィス契約費 1735円
- アップルミュージック契約費 1200円
- 生命保険、貯蓄型年金 25000円
- Hulu契約費 1026円
- カーシェア会費 1500円
- サプリメント月割り 4000円
- PSプラス契約費 600円
- アマゾンプライム 500円
- スタディサプリ(英語) 2480円
これ以外にも口座引き落としされている分もあるはずなのでもう少し増えるかもしれませんが、まずはわかりやすいところから調べてみました。
合計 7万円程度。
どうでしょう?多い方でしょうか?少ない方でしょうか?
何もせずに7万円が毎月消えていくのですからちょっと恐ろしいですね。
電気ガスに関してはうなぎのぼりです。
通信費は子供の分も含んでいますので、極端に高くは無いと思いますが、不明な引き落としが900円程あったので後で確認してみようと思います。使ってないものだったらラッキーですね。
一番費用の高いところは保険、年金関連ですが、これは後程説明したいと思います。
食費不明!外食はかなりの高頻度!
恥ずかしながら現在の食費に関してはよく把握していません。正直なところ、家計管理をほとんどしてきませんでした。これは大きな問題ですので、今からでも大まかに計算をしてみたいと思います。
外食頻度に関してはかなり高い方だと思います。夫婦共働き(だった)ということに加え、以前は二人とも通勤時間が1.5~2時間ぐらいかかる状態でした。(しかもお互いに正反対方向に移動するという)
妻は一時期、朝は新幹線も使っていました。新幹線代が出ないので行きのみ。帰りは在来線。
子供も中学時代から今も塾に通っており、帰宅が20時を過ぎることもしばしばです。
ですので、平日の塾の終わりに子供と外食したり、妻も帰宅途中に食事をして帰ってくることがありますので、かなりの頻度で外食をしています。3回/週ぐらいになります。
「主夫になったんならなんとかしなさい」
はい、ごもっともなご意見です。おっしゃる通りです。ぐうの音も出ません。
カレーやおでん等の、簡単に作れて夕食の時間がずれても食べることの出来るようなものを作り置きして頑張るようにしております。
なんか他に簡単にできる料理ありませんか?働きながらご飯を作っておられる方には頭が上がりません。
趣味や旅行の回数
続いては、趣味や旅行などに関しての費用になります。
大学生の頃からバイクに乗っていたので昔はそれが趣味でした。
滋賀県にも住んでいたのですが、その時はそこにバスフィッシングが追加され、さらに熱帯魚の飼育にはまり、オーディオ機器に夢中になり、ゲームにマンガと際限なく趣味があふれかえっていきました。
ワンルームのマンションからの引っ越しの際に4t車に荷物が乗らないという快挙も成し遂げましたが、
今ではかなり趣味も減りました。6畳の部屋に水槽が6個とか、今考えると自分でもクレイジーだと思います。人というものは歳とともに落ち着くものなのですね。
オートバイは置く場所が無くなり、バスフィッシングは釣り場から遠くなったことでだんだんと疎遠に。
サブスクで音楽を聴きながら、電子書籍のマンガや本を読むのが最近のお気に入りです。
電子書籍に切り替えてからは際限なく本が増えていくことは無くなったのですが、それでも以前までに買い貯めていた本は1000冊近くにもなりますので、メルカリに活躍してもらわないといけません。
ブックオフも使ったことはあります。しかしながら、仕方がないとはいえ本当にゴミのように扱われてしまいますので、ゆっくりと処分していこうと思います。
さて、話は戻って趣味と旅行にかかる費用ですが、毎月3万円ぐらいと見積もっておきたいと思います。
我が家では、家族で海外旅行に行きたいという要望があまり無く、行くなら「国内の温泉地でゆっくり」といった感じですので、毎月1万円を積み立てておくといったイメージでしょうか。
人によっては節約や投資が趣味だといった方もおられるでしょうし、趣味なくして何の人生か?という人もおられると思いますので、ここも人によって大きく異なる点かもしれません。
医療や保険の費用
固定費のところでも述べましたが、結構な割合を占めています。
民間の個人年金に関しては60歳で支払いが開始なのに加え、30年も前のものなので、今よりもかなり高い利回りで計算されているので、このままとすることにしました。
ガン保険や医療保険に関しては、日本での社会保障制度では必要ないという情報が多いです。公的な健康保険や高額療養費制度で、一般の病気なら対応可能なケースが多いからということです。
ただ、私の場合、親族のほとんどがガンで亡くなっていることを考えると、ガンの保険には入っておきたいところです。先進医療特約というやつです。
死因になるかどうかは別として、多分ガンにかかると思っています。。。
また、実は数年前にコロナで入院したことがあり、その時は医療保険から十数万の支払いをもらったという経験もあり、継続しようかなと考えています。(もちろんトータルではマイナスですけどね)
収入保障保険(死亡保険)に関しては掛け捨てでもともと65歳までしか入っていませんが、60歳少しで子供が大学を出て就職するようになりますので、そのタイミングでやめちゃってもいいかもしれません。
ということで、あと5年ほどはこのままの出費となります。
予備費や贅沢品への支出
ここはどう考えたらいいのか一番悩みました。ぼんやりとしていて範囲が広そうだったからです。
そこでまずは、予備費にどんなものを考えればよいかを一覧にしてみました。
病気やケガによる医療費: 予期せぬ入院や手術、長期的な治療が必要になった場合、高額な医療費が発生する可能性があります。
これに関しては、医療費のところである程度の保険を利用することで対応したいと思います。
家の修繕費: 老朽化した住宅の修繕や、突発的な故障(水漏れ、設備の故障など)が発生した場合、まとまった費用が必要になります。
こちらも当面はマンションの管理費、修繕積立で賄えると思います。
大型家電製品の故障は頭に入れておいてもいいですね。冷蔵庫や洗濯機が壊れると大変です。
家族の状況変化: 親の介護が必要になったり、子供の進学で急な出費が必要になったりする可能性もあります。
実は親の介護はすでに始まっており、老人ホームではありませんが施設に入ってもらっています。その費用も親自身の貯金や投資で賄えています。私なんかよりはるかに先を見据えて生活していたようです。私も子供に負担を強いることの無いようにしたいと改めて考えさせられます。
子供の学費が急な出費になることは稀かもしれませんが、海外留学したいと言い出したら結構戸惑うかもしれません。
経済状況の変動: インフレの進行や株価の大幅な下落など、経済状況の変動によって資産価値が目減りするリスクも考慮する必要があります。
インフレに関しては新NISAやiDeCoのような投資で対応していきたいと考えています。
株価の大きな下落に関しては当面の貯金でしのいでいくしかないですね。
資産形成期でなくなれば、株価下落時に強い連続増配株のような銘柄から、定期的に配当を受ける方法というのも分配投資としていいのかもしれません。
いずれにせよ、月の生活費の3~6か月分をすぐに取り出せる預金として確保しておく必要があります。
一方、贅沢品への支出してはどのようなものがあるでしょうか?
- 海外や国内の旅行
- 車の購入
- 友人や知り合いとの飲み会
- 大型テレビ
ほかにどんなものがあるでしょうか?
年齢を重ねてからのぜいたく品は、旅行が多いのかもしれません。
今回は旅行は趣味の部分に入れましたので、ここからは省けます。
これはあるあるかもしれませんが、退職してから外で飲むことが極端に減りました。交友関係が減ることが良いことなのか悪いことなのか微妙なところです。
車に関しては、住む場所によって贅沢品ではなく必需品となりますので、予備費に入れておくべきかもしれません。
まとめ:
いかがでしたでしょうか?
自分の現状を見える化するつもりでしたが、とてもとても一筋縄ではいきませんでした。
FIREを成功させるためには、目標生活レベルを明確にすることが不可欠です。理想のライフスタイルを具体的に想像し、現在の支出を把握した上で、ある程度の将来の変化を考慮した現実的な目標を設定したいと思います。
今回の記事で自分の大まかな支出を計算するつもりでしたが、食費の部分や固定費には入らない支出部分を確認することが出来なかったので、改めてそのあたりの確認を行いたいと思います。
また、定期的な見直しも忘れずに行う必要がありますね。
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
ではまた。



コメント